
学童保育で働くのに、資格って必要なのかな?
学童で働こうと思ったときに、資格が必要なのか気になる方も多いでしょう。
保育園、幼稚園、小学校…子どもに関わる仕事は資格を求められるイメージもありますよね。
実は学童保育は、資格が無くても働けます
資格を持っていないけれど、子どもに関わる仕事をしたい人にとっては、ありがたい職種ですよね。
この記事では、
- 学童保育の仕事に資格が必要ない理由
- どのような資格を持っていると採用に有利なのか
- 放課後児童支援員の概要
- 放課後児童支援員のとり方
上記の内容を解説します。
なるべく読みやすい形でまとめましたので、ぜひ最後までご覧いただき、学童保育で働くための知識をお持ち帰りください。
学童保育の仕事に資格は必要ない?

学童保育で働きたいと思っているのですが、資格は必要ですか?
 ニック
ニック結論:必要ないです
アルバイトやパートとして学童保育で働く場合、特別な資格は求められないことが多いです。
ただし、
- 放課後児童支援員
- 保育士
- 教員免許
- 社会福祉士
上記の資格を持っている人の方が、採用されやすいでしょう。
放課後児童支援員の資格があると、採用に有利な理由

資格を持っていると、どうして採用されやすいのですか?
 ニック
ニック資格を持っている人を学童に配置する義務があるからです
2015年に、学童保育で働く人のための資格が作られました。
それが、「放課後児童支援員」です。
そして学童保育に「放課後児童支援員」を配置することが、義務づけられました。
そのため、資格を持っている人は採用されやすいのです。
保育士・教員免許・社会福祉士を持っていると、採用に有利な理由

保育士などの資格も、採用に有利なの?
 ニック
ニックはい。有利です。その理由を説明していきますね
- 保育士
- 教員免許
- 社会福祉士
これらの資格を持っている人が採用されやすい理由。それは・・・
「放課後児童支援員」の資格を取りやすいから
「放課後児童支援員」の資格は、研修を受けてレポートを提出すると取得できます。
 ニック
ニック筆記試験や実技試験はなく、レポートで落とされることもほとんどないので、難易度はとても低いんです
とはいえ、
- 講義に遅刻する
- 講義中に寝てしまう
- レポートを提出しない
上記のようなことをすると、アウトです。

普通に受けていれば取れる感じなんだね
 ニック
ニックうん、その通りだよ
比較的かんたんに取得できる「放課後児童支援員」
しかし、
研修の受講条件がありまして、
- 保育士
- 教員免許
- 社会福祉士
これらの資格を持っている人は、認定資格研修を受講できます。
そのため、学童保育で採用される可能性が高いのです
学童保育は、資格がなくても働ける

私は資格を持っていないのですが、学童保育で働けますか?
 ニック
ニックはい、働けますよ
資格を持っていない人でも学童保育で働けます。
学童保育は「放課後児童支援員」を配置する義務がありますが、全員が資格を持っていなくても大丈夫なのです。
自治体により、何人配置しなければならないかが定められています。

自分で調べるのは大変そうだなぁ・・・
自分で探すのが一番ですが、何から調べて良いのか分からない方も多いですよね。
そこで、無資格でも学童の求人を探せるサイトをまとめました。
 ニック
ニック求人の検索方法も掲載していますので、よろしければお役立てください
放課後児童支援員とは、どんな資格?

「放課後児童支援員」に興味が出てきたのですが、どのような資格ですか?
 ニック
ニックひとことで言うならば、学童保育で働く人のための資格です
放課後児童支援員の資格は、小学生たちの放課後をサポートするための資格です。
放課後児童支援員は、放課後の子どもたちを支援する専門職といえます。
2015年に法律で定められたことで、学童保育施設には一定数の放課後児童支援員を配置することが義務づけられました。
放課後児童支援員(※)を、支援の単位ごとに2人以上配置 (うち1人を除き、補助員の代替可)
厚生労働省『放課後児童クラブについて』PDF資料
「子ども約40人に対して、放課後児童支援員を最低1名は配置しなければいけない」という内容
これが、2020年に「参酌すべき基準」に改正されました。

参酌すべき基準・・・?
 ニック
ニック十分に考慮した上で判断してね…という意味だよ
資格を求められない学童もありますが、「放課後児童支援員」を持っていると、採用に有利なのは間違いありません。
放課後児童支援員の資格を持っている人が、学童保育の求人に応募してきてくれることは少ないので、採用されやすいのです。
 ニック
ニック資格を持っている人が応募してきてくれると、採用側は嬉しいんです
特に、常勤指導員や正社員を目指すのでしたら、放課後児童支援員の資格は必須でしょう。
放課後児童支援員の資格取得方法

「放課後児童支援員」の資格に興味が出てきました。どうやって取ればいいのでしょうか?
 ニック
ニック順番に解説しますね
放課後児童支援員の認定資格研修の概要
「放課後児童支援員」の資格を取るためには、研修を受ける必要があります。
その研修が、放課後児童支援員認定資格研修(以下、認定資格研修)です。

認定資格研修?
 ニック
ニックうん。指定された会場で講義を受けて、レポートを提出するんだよ
認定資格研修の目的
認定資格研修の目的は、放課後児童支援員として働くために必要な、知識や技能を補完することです。
放課後児童クラブでの仕事をする上で、
- 最低限必要な知識や技能
- 基本的な考え方や心得
これらを学ぶことを目的としています。
基本的な知識や技能、考え方、心得を身につけることが目的
認定資格研修の対象者
神奈川県放課後児童支援員認定資格研修によると、研修の対象者は次の通りです。
認定資格研修の受講条件を満たしている人
その上で、
- 県内の学童保育(放課後児童クラブ)で働いている人
- 県内在住で、これから放課後児童支援として働きたい人

まず受講条件を満たさないといけないってことだね!
認定資格研修の受講条件
神奈川県の認定資格研修を担っている、東京リーガルマインドによると、受講資格は次のとおり
- 保育士の資格がある人
- 社会福祉士の資格がある人
- 教職免許を持っている人
- 学童保育など(放課後児童健全育成事業)で、5年以上働いた人
- 高校を卒業し、学童保育や保育園(児童福祉事業)で、2年以上働いた人
- 大学で、以下のいずれかを専修して卒業した人
- 社会福祉学
- 心理学
- 教育学
- 社会学
- 芸術学
- 体育学
具体的な目指し方は、こちらの記事が参考になります。
認定資格研修の内容
認定資格研修の内容は、以下の6分野、16科目です。
| 分野 | 科目 |
|---|---|
| 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解 | ① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 |
| ② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護 | |
| ③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ | |
| 2.子どもを理解するための基礎知識 | ④ 子どもの発達理解 |
| ⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達 | |
| ⑥ 障害のある子どもの理解 | |
| ⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解 | |
| 3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援 | ⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援 |
| ⑨ 子どもの遊びの理解と支援 | |
| ⑩ 障害のある子どもの育成支援 | |
| 4.放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力 | ⑪ 保護者との連携・協力と相談支援 |
| ⑫ 学校・地域との連携 | |
| 5.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応 | ⑬ 子どもの生活面における対応 |
| ⑭ 安全対策・緊急時対応 | |
| 6.放課後児童支援員として求められる役割・機能 | ⑮ 放課後児童支援員の仕事内容 |
| ⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守 |
 ニック
ニック神奈川県では、1日4科目(1科目90分)の講義でした。
申込み方法
各都道府県により、申し込み方法が異なります。
自分が所属している学童保育や、住んでいる都道府県のウェブサイトなどで確認するのが確実です。
まとめ
最後にこの記事をまとめます。
学童保育は、資格なしでも働けます。
ただし、
- 放課後児童支援
- 保育士
- 教員免許
- 社会福祉士
上記の資格を持っていると、採用に有利です。
資格を持っていない方でも、放課後児童支援を目指せます。
具体的には、
- 大学で以下のどれかを専修して卒業した人
- 社会福祉学
- 心理学
- 教育学
- 社会学
- 芸術学
- 体育学
- 高校卒業+2年以上、学童保育などで働く
- 5年以上、学童保育などで働く
資格や実務経験をお持ちでない場合は、次の2つのルートをおすすめします。
- 保育士を取得する
- 学童保育で働く
例えば、学童保育で働きながら、保育士の勉強をするのが良いでしょう。

学童で働きながら保育士を目指すなんて大変なんじゃない?

そうだよね。けっこう大変かもしれない。
しかし、学童保育でフルタイムで働きながら、独学で保育士を取得することは可能です。
実際に筆者はテキストを1冊購入し、保育士試験に挑みました。
テキスト1冊で挑戦できますし、たとえ不合格になってしまったとしても、保育の知識や考え方が身につくので、無駄にはなりません。
 ニック
ニック僕は保育士取得に、3年かかっちゃいました
ぜひ気軽にチャレンジしてみてくださいね。
学童保育で働く人が増えてくれると嬉しいです!
学童保育のリアルな仕事内容を知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
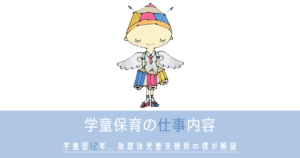
学童保育の求人を探したい方はこちら!学童保育の求人数をランキング形式でまとめました。

学童保育指導員が抱えがちな悩みについて知りたい方は、こちらの記事からご覧ください。
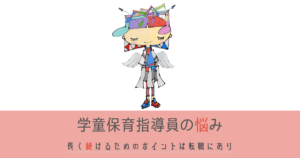
最後までお読みいただきまして、どうもありがとうございました!
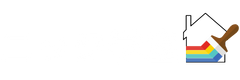
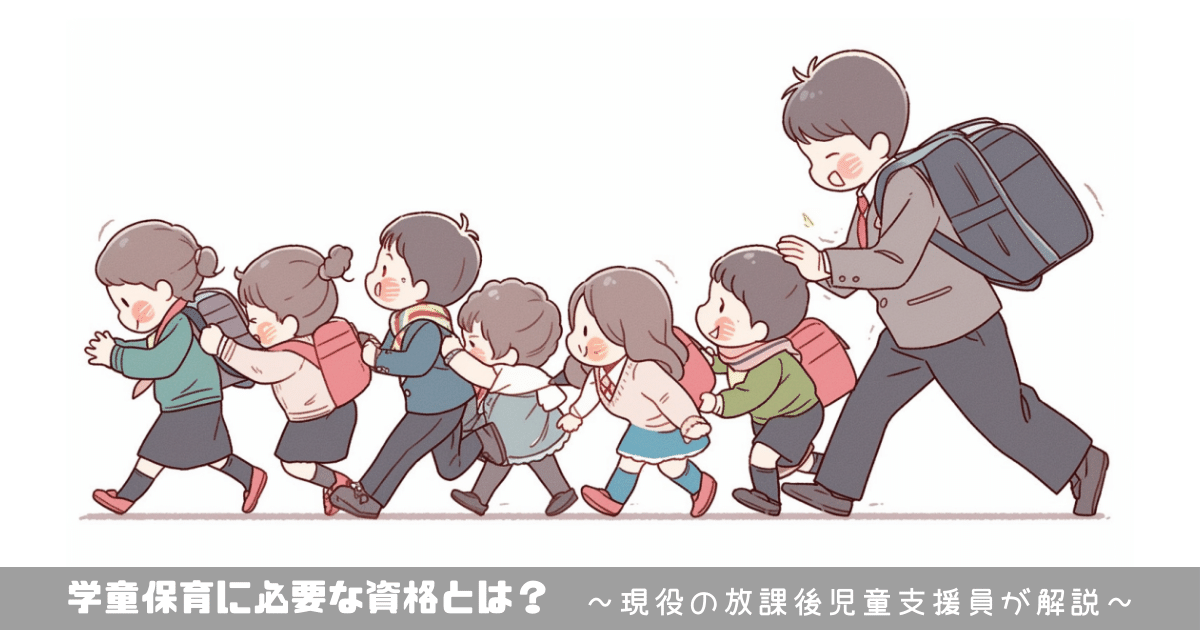
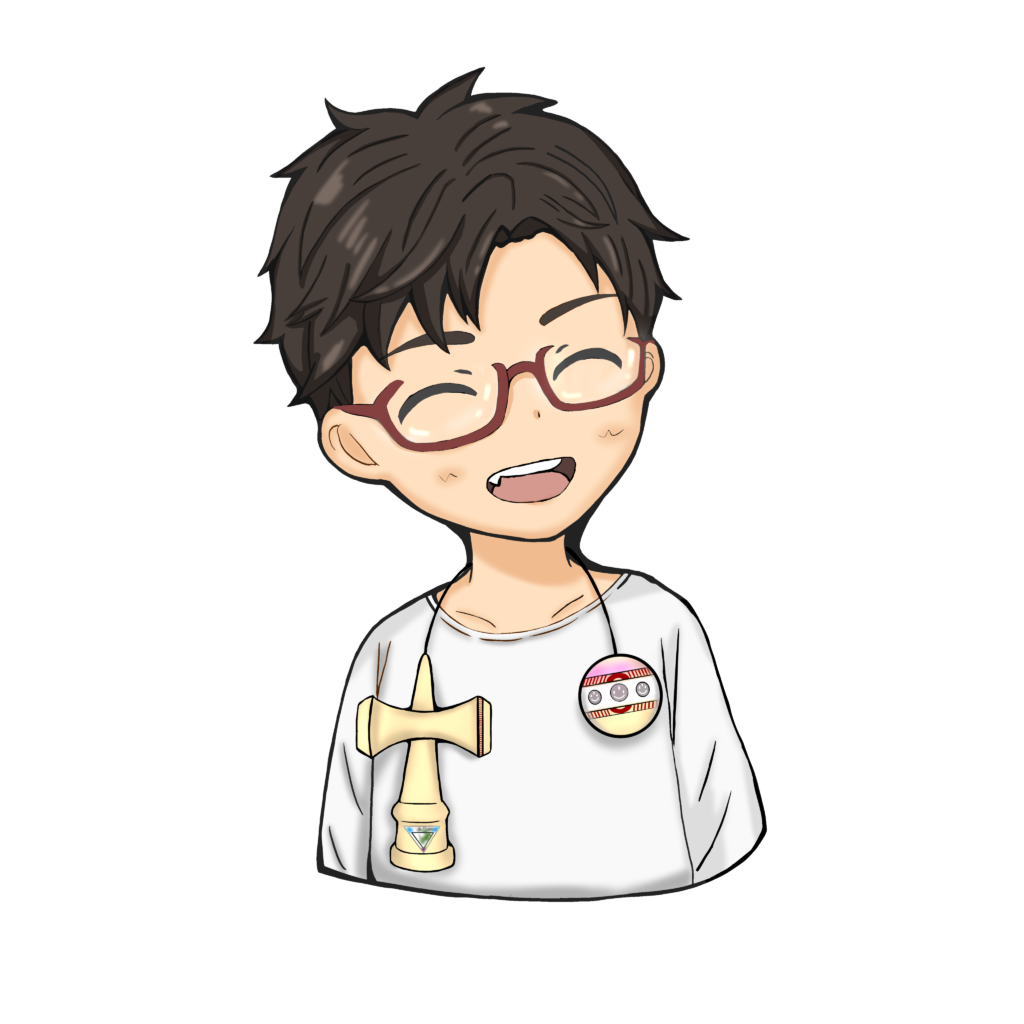


コメント